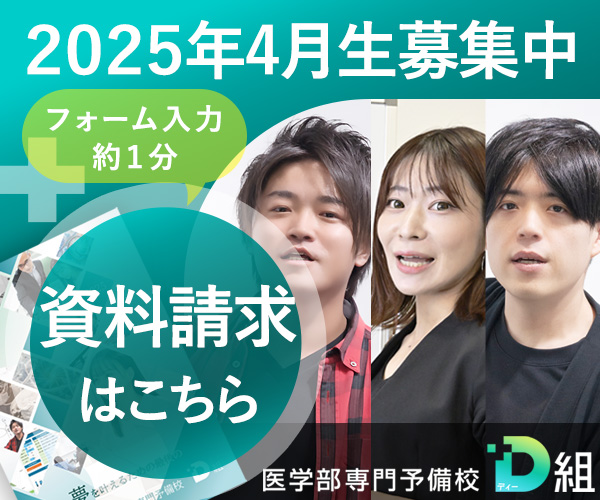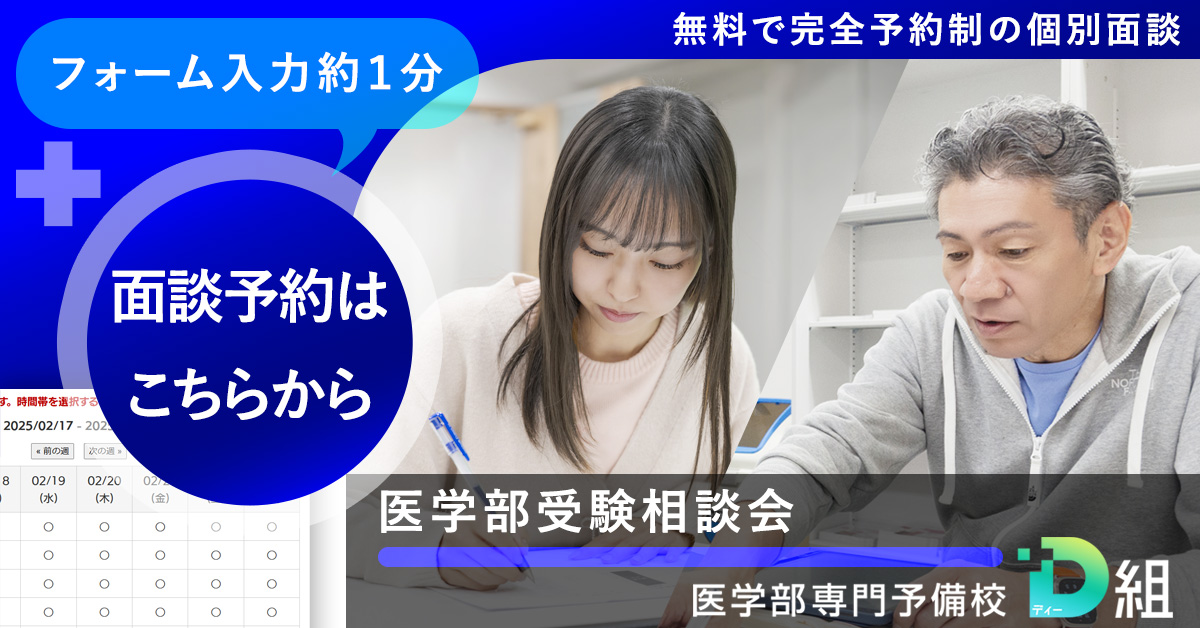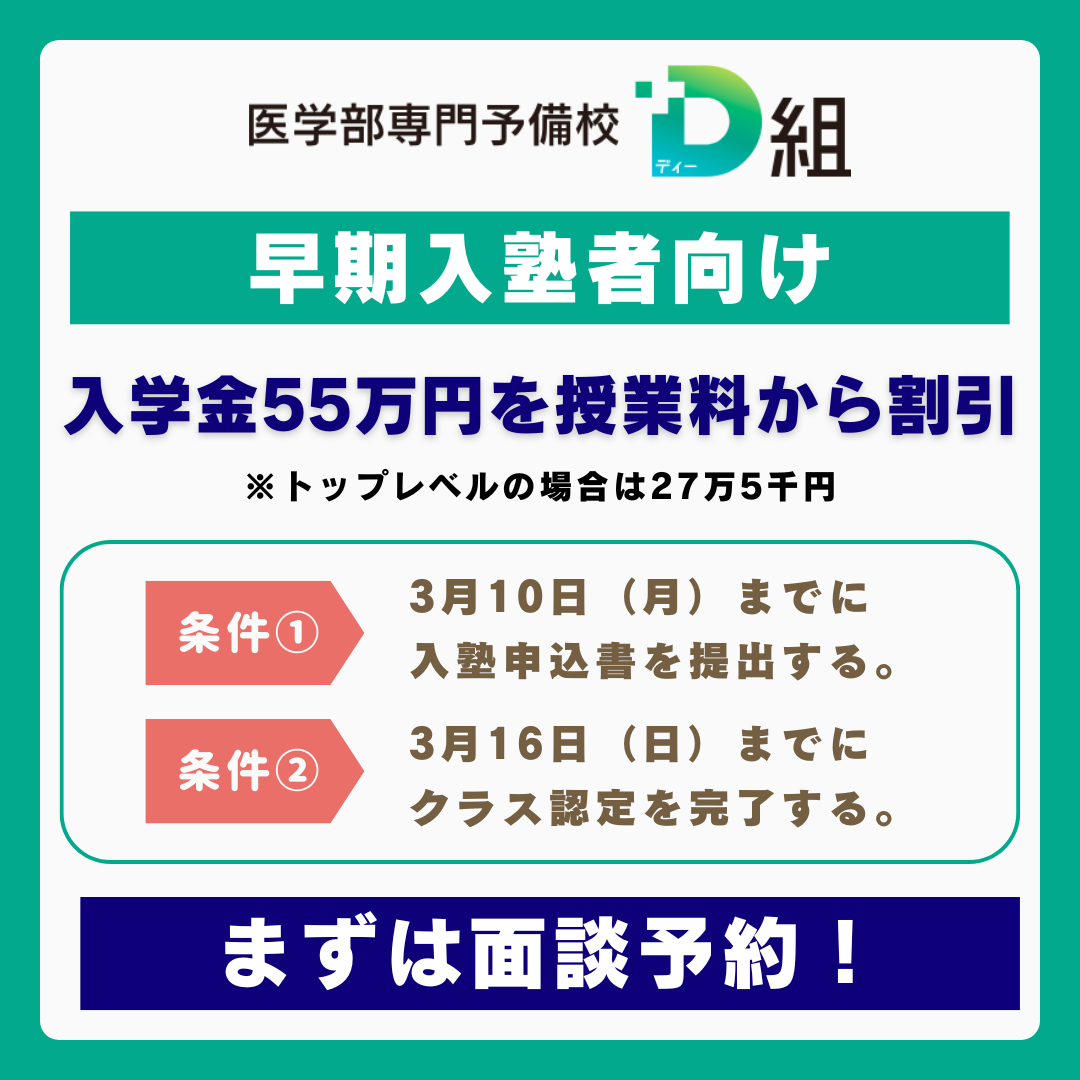日本医科大学医学部生物(2024年度/一般)-入試情報
出題形式
答えのみ記述(50%)、論述(50%)
試験時間
60分(理科2科目120分)
難度(5段階)
2.7(標準)
分量(必要時間)
58分(標準)
合格に要する正答率予想
71%
大問数
3問
出題内容
系統と進化、生命現象と物質、生殖と発生、生物の環境応答、生態
求められているもの
例年 第1問と第2問はごく基礎的な知識中心で、分野横断型である。これに対し、第3問は本格的な実験考察型問題である。第3問については、2024年よりも高難度の問題を出題することが珍しくないため、解析型問題に対する相応の対策が不可欠である。基本的な知識を有するだけでなく、解析力や考察力、論述力の高い学生を大学側は求めている。
今月は日本医科大学生物の過去問に精通されている医学部専門予備校D組生物科講師の牧島 央武先生に入試対策をお聞きしました。
第3問は明らかに難度が高い
牧島 央武先生よろしくお願いいたします。早速ですが近年の日本医科大学の生物には特別な傾向はありますか。傾向を表す具体的な出題事例があれば教えてください。

日本医科大学は例年大問3題で構成されていますが、第3問が明らかに他の大問と比較して難度が高くなっており、扱われるテーマも動物生理、遺伝子を扱ったものが出題されることが通例になっています。出題の内容を比較しても、第1問、第2問については、前半は単純な穴埋め問題、知識論述などアプローチしやすく、後半は平易な考察問題となっており、受験生の実力が反映されやすい構成と言えます。一方で、第3問はリード文、そこに付される実験設定とそのデータが膨大で、さらに一問目からそれらの情報を読み取らないと解けない問題となっており、予備動作なく高いハードルが課されます。生半可な力では、まったく太刀打ちできないでしょう。
平易な問題をさばきながら難問にも挑戦する
牧島 央武先生としては、その傾向にはどういった大学の意図が現れていると想像されますか。

まず第1問、第2問は医学部への関門としての最低条件であり、これらに対応できない受験生は門前払い、ということです。しかし、第1問と第2問を完答したとしても、それだけでは合格は確約されないでしょう。第3問は日本医科大学から受験生への挑戦状であり、そのチャレンジ精神を見極めているのではないかと思います。第3問については、問題の導入で多くの受験生が諦めてしまうほど高難度です。しかし、60分の試験時間は第1問と第2問だけを解答するには長過ぎで、第3問まで完答するには短過ぎます。限られた時間のなかでいかに難問に食らいつけるか、その立ち向かう姿勢が求められています。第1問、第2問については、第3問の解答に十分な時間をまわせるよう、いかに安定的に、いかにスピーディーにこなすか、という問題になります。平易な問題をさばきながら、腰を据えて本格的な考察問題に取り組む、というマルチタスクの感覚も必要な要素です。
考察の底力を高めてくれる難問
日本医科大学医学部の過去問を使った効果的な学習法があれば教えてください。
第1問、第2問については、一通りの内容を学習した直後でも取り組める問題です。早い段階でチャレンジして、解ける感覚をつかむのに利用しましょう。一方で、第3問はある程度自信が持てるようなってからのチャレンジが良いです。時間無制限で、骨太の考察にしっかりと向き合ってみてください。苦労が大きいですが、考察の底力を高めてくれるでしょう。
直感を明文化する
現在、まだ合格水準に足りていない受験生が日本医科大学医学部の合格水準に達するための努力としてはどういったものが考えられますか。
まずは生物に関する一通りの知識体系が必要です。考察問題が合否を分けるといっても、リード文から情報を抽出する段階で基本的な生物の知識が必要になります。マニアックな内容まで手を出さなくてもよいので、教科書、資料集レベルの内容は押さえておきましょう。次に実験考察問題への取り組みです。日本医科大学の第3問では、いくつもの実験が提示されます。2025年度は実験1~7、2024年度と2023年度は実験1~8とかなりの奥行きのある大問になります。このような問題に対応できるようになるために、まずは普段の演習で実験考察問題に取り組む際に、実験ごとにどのようなことが分かったのか、簡単な短文、または図や絵にまとめるようにしていきましょう。頭で分かったつもりでも、それを残していかないと状況の理解を積み重ねることができません。「直感を明文化する」、この作業を心掛けてください。
「諦めの悪い人」が評価される印象
これまで日本医科大学医学部に合格してきた受験生にはどういった特徴がありましたか。
生物を単なる暗記科目と考え、一問一答形式の問題に慣れてしまっている人は日本医科大学の生物と相性がとても悪いです。問題の導入ではまったく全体像が見えませんが、それでも一つ一つの実験を通じて少しずつ霧を晴らしていける、長い文章と冗長な情報に食らいついていける、「諦めの悪い人」が評価される印象です。
時間配分を意識
日本医科大学医学部の入試当日に気を付けてほしい点はありますか。
大問3題で第3問が重めの実験考察問題、という構成は例年のものになっていますが、変更がないとも限りません。まずは試験問題全体を見通して、形式に変更がないことを確認して、時間配分を意識しておきましょう。変更があっても焦らずに。皆同じスタートラインです。
成長したい!という欲
いよいよ冬期、直前期を迎えラストスパートに入る受験生に熱いメッセージをお願いします。

自分の成長のためだけに一年を使えることはとても幸せなことです。成長したい!という欲をもってください。
新次元の群像劇
最後に牧島 央武先生の心の名作を教えてください。
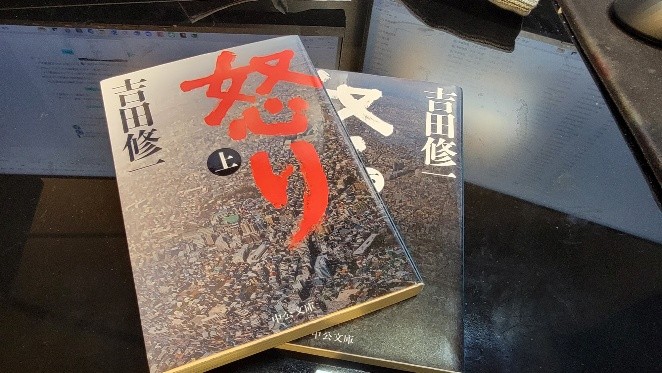
好きな作家は、吉田修一先生です。「パレード」や「怒り」などがおすすめです。どちらも暗い群像劇ですが、たまにはそうやって沈むのも悪くないですよ。
なるほど、牧島 央武先生ありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。
医学部専門予備校D組では現在の成績に関係なく10人程度の少人数クラスで牧島 央武先生の生物の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能なきめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。